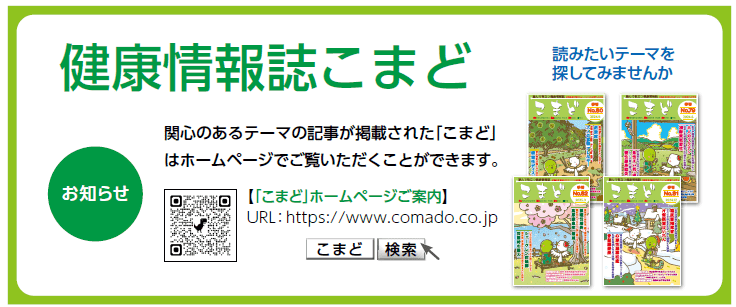Dr.中原の健康こぼれ話66

西武学園医学技術専門学校 東京校 校長/医学博士
中原 英臣 先生
日本で生まれた 栄養学
栄養学という分野がありますが、栄養学の創始者は「栄養学の父」とも呼ばれている佐伯矩ただすです。佐伯が栄養学を創設するまで、栄養といえば炭水化物、たんぱく質、脂質が「三大栄養素」と呼ばれていました。
そこに加わったのがビタミンという栄養素です。体内で合成できないビタミンは、食料から摂取しなくてはなりません。そのためビタミンが不足すると「ビタミン欠乏症」といいます。脚気がビタミンB1の欠乏症であることに気が付いたのも日本の高木兼寛です。
ビタミンB1を発見したのは日本の鈴木梅太郎です。鈴木は1911年にコメの糠からビタミンB1であるオリザニンを発見しましたが、論文が日本語だったために、国際的には評価されなかったのです。
日本は栄養に関する研究で世界をリードしていたのです。そうした栄養に関する研究を世界に先駆けて医学から独立させたのは佐伯でした。日本の自然科学はすべて明治のはじめにヨーロッパから輸入されましたが、日本で誕生したのは栄養学と地震学だけです。
「栄養」という言葉を提唱した佐伯は914年に世界で最初の栄養研究所や栄養学校を創設し卒業生に栄養士という資格を与えます。「偏食」「栄養食」「栄養指導」などの用語も提唱しました。栄養学の基礎となっている1日2400キロカロリー、蛋白質80グラムという栄養基準を決めました。その後、佐伯は発育期にある学童の栄養を向上する目的で「学校給食」をはじめました。
いまでは世界中に栄養研究所や栄養学校がつくられ、栄養学という学問は大きな分野となっています。佐伯矩は日本人が誇る科学者といえます。