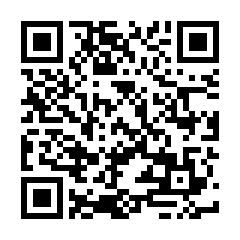下澤達雄先生の臨床検査かわら版 『高齢者の降圧目標が変わる!?』
高血圧治療ガイドラインの改訂で
最新の研究成果に基づいた標準治療を推奨する治療ガイドライン。
このたび、高血圧の治療ガイドラインが改訂されました。
どんな点が変わったのでしょうか?

国際医療福祉大学医学部 臨床検査医学 教授
下澤 達雄 先生(しもさわ・たつお)
2017 年より現職。専門は高血圧学、臨床検査医学、内分泌学、腎臓病学。日本高血圧学会理事、日本心血管内分泌代謝学会理事、日本臨床検査医学会理事、日本クラリネット協会副理事長などを務める。「秋の味覚や芸術の秋を楽しみながら、健康の基本、生活習慣を(食事以外にもリラクゼーションなども)見直したいと思っています」。
高血圧治療が変わる?
「生活習慣の改善のうち、何が有効で何が有効ではないのか?」
「新しい治療薬は本当に効果があるのか?」
「高齢化社会に向けて高血圧の予防、治療はどうあるべきか?」
高血圧治療に関するこのような疑問や問題点にこたえる研究の成果が近年続々と発表されています。
それらに統計学的処理を行い、本当に正しい結果かどうかを吟味するメタ解析を行ったうえでまとめたものが『高血圧治療ガイドライン』です。おおよそ5 年ごとに改訂されていますが、今年、2019 年から6 年を経て、『高血圧診療ガイドライン2025』が発行されました。今回の改訂で大きく変わったのは、治療薬の選択と高齢者の降圧目標です。その中から特に高齢者の降圧目標について紹介しましょう。
治療は個人の状況に合わせて
高齢になると高血圧になりやすいだけではなく、動脈硬化や心機能の低下、腎機能の低下、認知症などを合併しやすくなります。特に動脈硬化がある場合に血圧を下げすぎると脳や心臓に血液が十分に行かなくなり、転倒、意識障害など、弊害のほうが多くなることが懸念されています。
2019 年のガイドラインまでは75 歳を超える高齢者の降圧目標は140/90mmHg とされてきました。しかし、その後の研究成果から、高齢者を年齢で一律に区分すべきでないというエイジフリーの考え方が取り入れられ、今回のガイドラインでは、加齢に伴う個人の特徴に基づいた降圧目標や治療方法の選択が推奨されてます。
自力で外来通院が可能なくらい元気であれば130/80mmHg を目標とし、認知症や身体機能の低下により外来通院の際にも介護が必要であれば140/90mmHg を目標とします。さらに外来通院が難しい場合には
150mmHg 程度を目標として、120mmHg 以下に下げないように注意をすることになっています。がんなどでエンド・オブ・ライフ(終末期)のステージにある場合には個別の判断も必要で、降圧薬の中止も考慮すべきとされています。また、80 歳以上で血圧が150mmHg 未満であれば、薬を減らしても大きな影響がないことが明記されています。
ここで注意したいのは、降圧目標は達成して初めて意義があるものだということです。ですから、少し高めでもいいとは思わないでください。さらに、薬は漫然と飲むのではなく、家庭で血圧を測定し、下がりすぎている場合は主治医と相談することが推奨されます。ガイドラインが改訂されると、さまざまな情報が入り乱れます。ネット上を偽情報がにぎわせることもありますが、そのようなものに惑わされることなく、自分自身の健康を守っていきましょう。
※日本高血圧学会公式キャラクター、良塩(よしお)くんの部屋
このチャンネルでは、血圧の大切な情報をわかりやすく発信しています。
https://www.youtube.com/channel/UC7ytIXmu83C5BAlqpEpIuLg